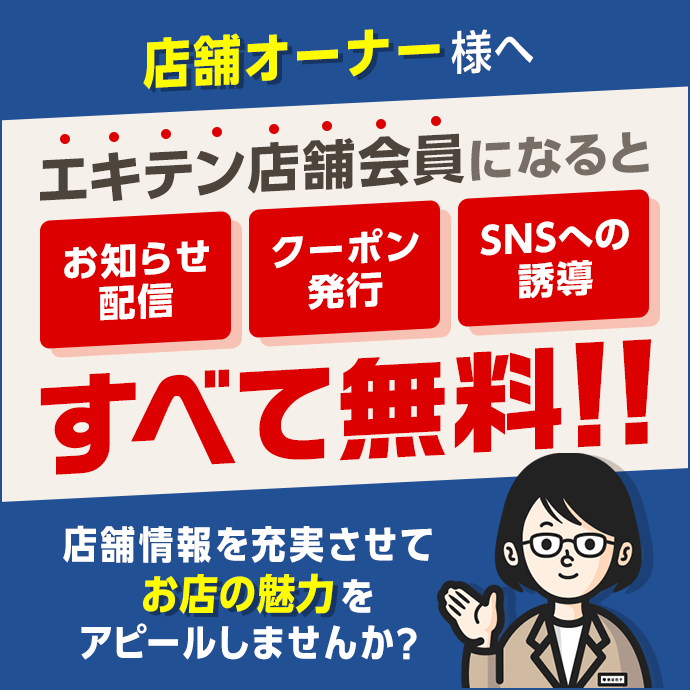口コミ
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。四国八十八ヶ所霊場の第三番札所です。行基菩薩の開基と伝わる古い歴史を持つ寺院です。観音堂の隣の祠に“黄金の井戸”があり、この井戸を覗き込み、影がはっきり映れば長寿、ぼやけていると短命という言い伝えがあるとのことでしたが、怖いから覗くのをやめました。天井に綺麗な花鳥が描かれている護摩堂や朱色が美しい多宝塔、観音堂、義経が弁慶の力試しに持ち上げさせたと伝えられている“弁慶石”など見所の多い寺院でした。
四国八十八ヶ所霊場の三番札所となります。
日照りによる水不足に苦しむ人々のため、空海が掘ったとされている黄金の井戸が残る寺院になります。
そのほかにも、源義経主従の伝説や長慶天皇の御陵石など、見どころが多くて良いです。
四国八十八ヶ所霊場の第三番札所です。行基菩薩の開基とされています。境内には、覗き込み影がはっきり映れば長寿、ぼやけていると短命という言い伝えがある“黄金の井戸”や義経が弁慶の力試しに持ち上げさせたと伝えられている“弁慶石”があり、静かで穏やかな雰囲気がありました。
この時期、境内の周辺に地生(?)しているアジサイがとてもステキです。
総広くない境内に、堂宇がひしめきあいます。
歩き遍路ですと、寺に東側の田んぼ道から寺に入りますが、今は歩く人も少ないでしょうね。
山門は20年ちょいまえに新しくなり、現在は風景になじんできています。
山門右手にある、石碑は必見です。
国道12号から看板にしたがって右折します。歩き遍路用の道と、車・バイク等で進むことが出来るみちで多少違いがあるようです。車道だと一度坂を登った後に下ります。左手に境内らしきものが見えてきて「ここかな?」と思ってしまいますが、そこは神社です。神社の入り口から少し入ったところに金泉寺の山門があります。
仁王門を入った正面に本堂、右に大師堂があります。また仁王門のすぐ右には観音堂があり、観音堂のすぐ右には井戸があります。この井戸は、弘法大師が水不足で困っていた住民のために掘ったものと言い伝えられています。井戸を覗いて水面に自分の姿が映ると長生きでき、映らないと3年以内に死んでしまうと言われているそうです。観音堂を撮影している間に井戸の存在を忘れてしまい、結局覗きませんでした。
デジカメとケータイの写メであれこれ撮影して撮ったつもりになっていたのですが、ケータイでは2枚しか撮影していなかったので、画像はありません。
本堂の裏にも朱色の塔があり、境内の中では一番派手に見える建物です。
納経所は本堂の左手にあり、ちょっとした庭園のような場所があります。その一角に、弁慶石と呼ばれた石があり、源平合戦で源義経が戦勝祈願に金泉寺に立ち寄ったとき、弁慶がその石を持ち上げて士気を高めたと言われています。非現実的な大きさではなく、屈強な男が2、3人集まれば何とか持ち上げることができそうな大きさにリアリティがあります。
四国の三番札所です。板野駅から、20分〜30分かかります。このお寺は、井戸があります。覗いて姿が映ればいいことありますよ。あとは、弁慶が力試しした弁慶の力石があります。2番札所からは、歩きで約1時間ほどでつきます。車だと15分くらいです。