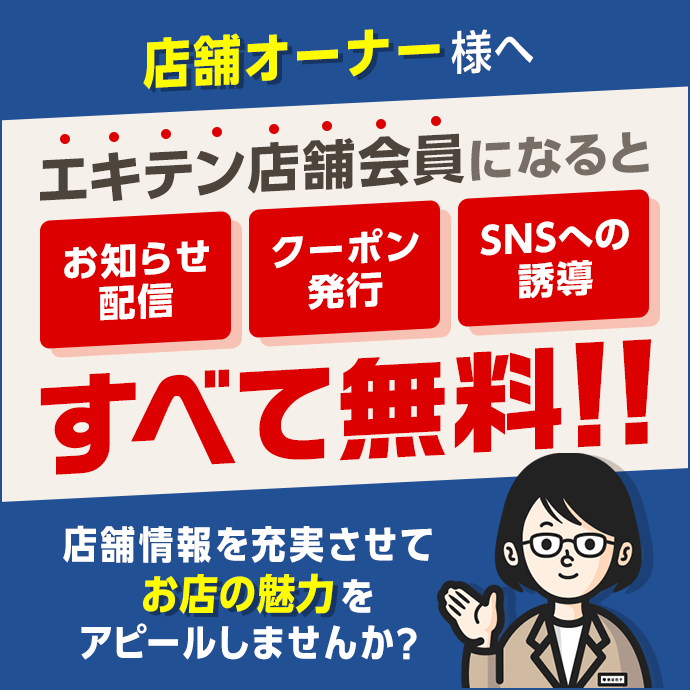口コミ
807年に空海によって開創された
1200年に及ぶ歴史を持つ修禅寺は
修善寺の地名の由来となった寺院でもあり、
街の中心にあります。
町の名前は修「善」寺、お寺は修「禅」寺です。
桂川ほとりの道から石段を上ると、
山門には歴史を感じさせる仁王像が鎮座していました。
入場料300円の宝物殿も大きくはないですが
なかなか見ごたえがありました。
手水は温泉になっており、
さすが温泉街にあるお寺と思いました。
桂川から上がってお寺がありました。地元では通称で「しゅうぜんじ」と呼ばれているそうですが、正しくは「しゅぜんじ」だそうです。
弘法大師の開基なのでかなり古い創建のお寺です。温泉地を開いたのも、弘法大師の伝説があり、独鈷(とっこ)の湯がそれです。伊豆で最も古い源泉と言われています。
真言宗から、その後、臨済宗、さらに曹洞宗と宗派が変わりました。
お寺のお清め水は、温泉でした。「大師の湯」と呼ばれているそうです。
右隣の日枝神社は、明治期の神仏分離で切り離されていましたが、もとは一体でお寺の鎮守社でした。
お寺の宝物館には、頼家の画像、岡本綺堂作のお面もあり、拝観料がかかります。
頼家の墓、指月殿、十三士の墓など、悲しい事績はいつまでも傳らえます。
修善寺駅からですとバスで行かないとかなり距離のある場所にあります。
こちらのお寺は観光スポットにもなっており、周りにもお土産屋さんなど、この地域でしか味わうことの出来ない商品が多数あります。
近くには川もあり、かなり風情はあると思いますよ♪
修善寺に来たら、修禅寺(笑)
寺内は期待してるほど、広くはないと思いますが、歴史について学ぶことが出来ますよ♪
修善寺を訪れて修禅寺に行かない訳には行かないと訪れました。地名の修善寺と寺名の修禅寺も初めて知りました。修禅寺は、曹洞宗の名刹。夫婦揃って曹洞宗の坊主の孫なので縁も感じます。807年に弘法大師創建らしい。重要文化財の木造大日如来座像もあります。歴史を感じる素晴らしいお寺です。
伊豆の修善寺温泉街の中心にある曹洞宗の名刹です。
807年に弘法大師が開いた歴史のあるお寺とのことです。
ここの地名の由来ともなったお寺なのですが、
修禅寺の「禅」がその地名では「善」となっているのが、
すごく意味ありげでちょっと感心しました。
山門のところにある金剛力士像や、重厚な本殿、
そして龍の口から温泉が出る手水舎など
いろいろと見所も多いです。
観光客が多いのですが、一抹の寂寥感を覚えるのは
修禅寺に幽閉され、暗殺された源頼家公の話が
頭をよぎるからでしょうか。
湯汲み式やキャンドルナイト、華麗な花火大会と
いろいろなイベントも行なわれていて
この観光地を代表するお寺となっています。
手水が温泉
- 投稿日
807年に弘法大師が建てたと言われているお寺さんです。
そう大きなお寺さんではありませんが
緑が豊富なので、季節ごとの風情を感じれてなかなか良いです。
こちらで面白いのが手水処の龍の口から温泉が出ている所。
温泉地ならでは、という感じですね。
川沿いにある、独鈷(とっこ)の湯もかなり有名です。
弘法大師がこの地を訪れた際、
冷たい川の水で病の父の体を洗う少年の姿に心を打たれた弘法大師が
手にしていた独鈷杵で河中の岩を打ち砕いて
この温泉を湧出させたのだそう。
現在、独鈷の湯は足湯にリニューアルしてしまったそうですが
昔は無料の入浴施設として自由に入れていました。
更衣室なんてものはなく、壁もほぼスケルトン状態でしたので
勇気の無い私は入れませんでしたが(笑)、
地元の方や、男性の方は利用していたようです。
場所も昔と違い少しずれた?というウワサ。
徐々に変わっていってしまうのですねー。
●小さな神社や寺院などを見て回っても、多少の感動はあるが、やはり、でかい寺院などを拝観すると、ひときわ感動が違います。
●807年開創とは言うけれど、都から遠く離れた辺境の地で、よく建立する気になったな。宮大工は、京都から呼んだのかな。工事も、大変だろう。
●で、かの有名なドッコの湯があります。もう、丸見えなので、全裸で入浴するには覚悟がいります。色々と物議がかもされているみたいですが、当時、そんな問題はありませんでした。日中、勇気を振り絞って、全裸で入浴しました。すでに、おばさんが2人、入っていました。自分の度胸・根性が、あまりにも小さすぎました。