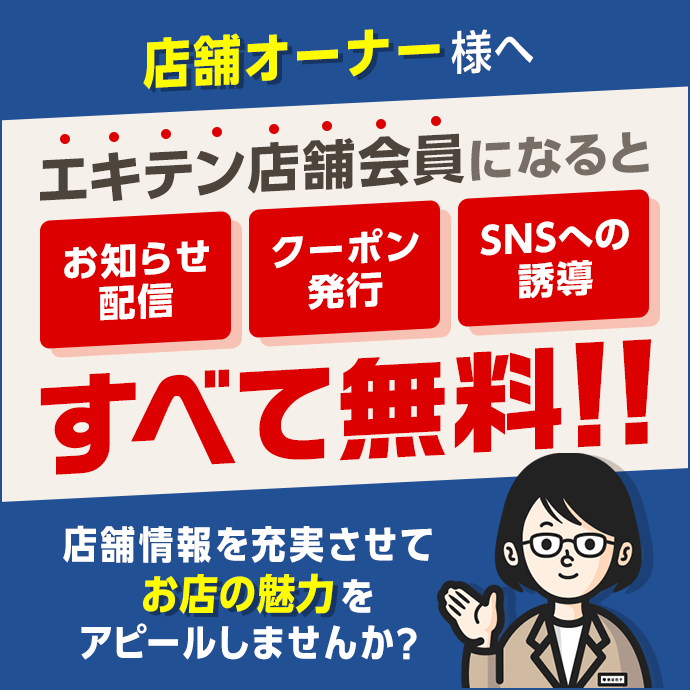口コミ
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。四国八十八ヶ所霊場の第三十四番札所です。寺名は弘法大師が唐から持ち帰った五穀の種を蒔いたことに由来しているそうです。ご本尊は薬師如来さまですが、安産、子育ての守り神として信仰されているそうで、妊婦が柄杓をもって詣るとお寺で底を抜いた柄杓を安産祈祷してお札を添えて授けられたものをお寺でいただいて、妊婦は床の間に飾り、無事に安産すればお礼に底のない柄杓を寺に納めるという風習があり、子育観音像の周りには底のない柄杓がたくさん吊るされていました。
四国八十八ヶ所霊場の第三十四番札所です。本尾山・朱雀院と号す真言宗豊山派の寺院で、創建は弘仁年間(810年 – 824年)、弘法大師開基と伝わる古い歴史を持っています。石柱門を入ると鐘楼、その先に大師堂、地蔵堂、子安観音があり最も奥に本堂があります。「安産の薬師さん」として親しまれている寺院で、妊婦が柄杓をもって詣ると、お寺では底を抜いて二夜三日の安産祈祷をし、お札を添えてかえす。それを妊婦は床の間に飾り、無事に安産すれば柄杓を寺に納める習わしがあり、子安観音像の周囲には沢山の底のない柄杓が納められていました。
本尊は薬師如来像とのことで、健康祈願に訪れました。
薬師如来というと、健康祈願や病気平癒のイメージが大きいですが、
ここでは、安産祈願で有名のようです。
子育て観音様もおられました。
奈良や京都で、神社仏閣を数多く参拝してきましたが、門から長い階段を登らなければならないときが多く、健康な人でないと難しいなぁとの印象が強いです。
一方、こちらは、少し足腰が弱くなっていても、門から本堂まで距離も近く、段差もなさそうなので、どなたでも伺うことができそうです。
もちろん、歩き遍路の方も多く見ました。
バスツアーで来られた方や、外国人のお遍路さんもいらっしゃるようです。
今年の恵方の方角にあたるので正月過ぎに行きましたが、神社ではなくお寺です。飛鳥時代に大和の(蘇我馬子で有名な日本で最初のお寺の)飛鳥寺を作った技術者が自国に航海して帰る途中に海上で嵐に合い山を越えて仏像を奉納したのがこのお寺の起源らしいです。今でも付近の漁港は、台風時に防波堤が破壊されるほどの大波がきます。連続して台風が上陸した2004年秋の月刊ニュートンでもその波が特集されていました。子供の頃にも親父の実家の近くなので来ましたが、空海の四国88個所の一つぐらいの規模でしたが、今では観光バスが何台も停めれるような駐車場のある観光スポットに成っています。携帯電話で動画も撮りました。妊婦がお礼に柄杓の底を抜く風習があるようですが、自分には、どういう起源があるのかさっぱりわかりません。
四国八十八ヶ所霊場の第三十四番札所
- 投稿日
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。高知市街から車で30分足らず、三十三番札所の雪蹊寺からだと10分あまりのところにあります。
弘法大師が唐から五穀の種を持ち帰り、ここに蒔いたことから“種間寺”と言う名前になったそうです。山門は無く、石柱門を入ると鐘楼があり、その先に大師堂、地蔵堂、子安観音があり最も奥に本堂があります。
ご本尊は“安産の薬師さん”で、妊婦が柄杓をもって参拝すると、お寺では柄杓の底を抜いて安産祈願をし、お札を添えてかえす。それを妊婦は床の間に飾り、無事に安産すれば柄杓を寺に納めると言う珍しい風習があるそうで、子安観音像の周りには沢山の底の無い柄杓が奉納されていました。
無料の駐車場があります。
雪蹊寺までの道には飲食店が点在していたので、種間寺へ行く道中で昼食を取ろうと思い出発しました。しかし県道279号は田圃の横を走るような農道的道路で、いくつか店舗はありましたが飲食店以外でした。探しながら進んでいる内に種間寺に到着しました。
こちらも山門はなく、石柱が入口に立っているだけでした。
弘法大師が唐から帰ってきた際、この地に立ち寄り寺を建立し、唐から持ち帰った五穀を境内に播いたことから種間寺とついたそうです。
門を入って右に広い駐車場があります。駐車場から門に戻り左奥に向いて伸びる参道を進んでいきます。右手に大師堂、正面に本堂があります。
また、大師堂の向かいあたりにある子育観音は安産祈願の御利益があり信仰が厚いそうです。妊婦が柄杓を持ってお寺を詣ると、お寺では柄杓の底を抜いて、安産祈祷をした後柄杓を返します。無事に出産を終えたら、底の抜けた柄杓をお寺に奉納するというしきたりがあるそうです。子育観音周辺の柱には奉納された底抜け柄杓がずらりと立てかけられていました。
納経を済ませたのが午後2時頃、八十八カ所だけなら近くに後2寺あるので時間にゆとりがありますが、別格三十六不動の霊場が高知市内に2カ所あり、残り時間でどちらに進もうか悩みました。次回の移動を短くする為に、高知市内に引き返すような形で別格不動をお参りすることにしました。