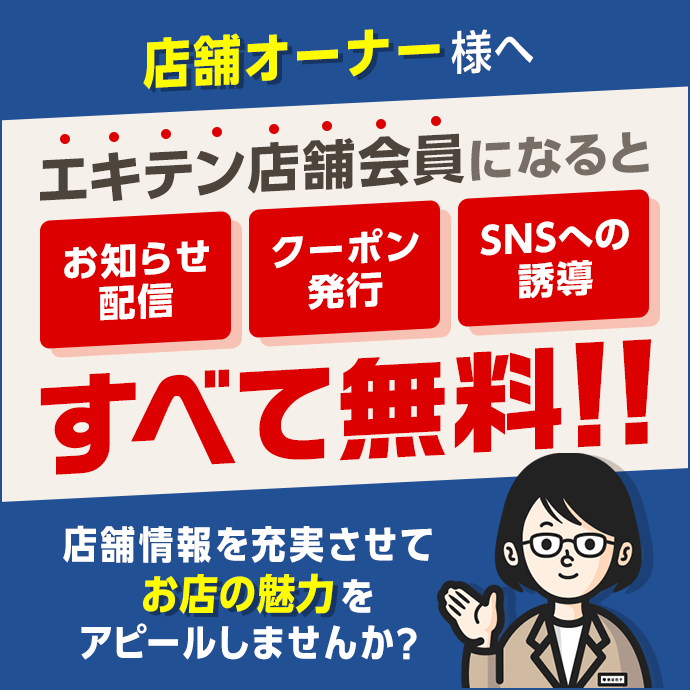口コミ
四国八十八箇所巡礼の旅で参拝しました。JR今治駅の西3kmほどのところにある真言宗豊山派の寺院で四国八十八箇所霊場の第五十四番札所です。駐車場から古びた仁王門を通った先にあるけやき造りの山門は、明治初期の今治城取り壊しの際に城から移築したものだそうでとても見応えがあります。本堂は破風が立派で、本堂の下にはほほえみ地蔵の周り並ぶたくさんの水子像が祀られているのが印象的です。また、大師堂の前には錫杖があって回すとご利益があるそうなので回してお参りさせて頂きました。
四国八十八箇所霊場の第五十四番札所です。近見山・宝鐘院と号す真言宗豊山派の寺院で、創建は養老4年(720年)、開基は行基と伝わる古い歴史を持っています。今治城の城門の一つを移した見応えのある総欅造りの山門を潜ると正面に本堂、右手に庫裏、左に含霊堂、本堂の左の石段を上ったところに大師堂があります。境内のところどころにベンチがあり休めるようになっていて楽しくお参りさせて頂きました。
松山にある三十三番札所である円明寺から海沿いの道を延々35km歩いてやっとついたのがここ延命寺です。札所の間隔が開くと心が折れそうになります。ここからは今治市内では近くに札所が続くので、足取りも軽くなります。
第五十四番札所
- 投稿日
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。今治市の郊外にあり、今治の中心部から車で十分足らずのところにあります。第五十三番札所の圓明寺から車でなら1時間あまりかかります。
もともと明治維新まで“圓明寺”だったそうですが、同じ寺名の五十三番の“圓明寺”との間違いが多いから、江戸時代から俗称として使われていた“延命寺”に改めたそうです。
お寺は周囲を田園に囲まれた静かなところにあります。もとは、今治城の城門であったという山門をくぐると正面に本堂、右手に庫裏、左手に含霊堂があり、本堂左の石段を上ったところに大師堂があります。見所の一つに、再三の火災から逃れて“火伏せ不動尊”と呼ばれる宝冠をかぶった珍しい不動明王像があります。また、鐘楼にある鐘は、周囲にお寺の歴史が彫ってある、1704年に造られたと言う古いもので、市の文化財にしていされています。是非、ご覧になって下さい。
駐車料金は志納金制です。
レイトショーを見てネットカフェに泊まり、9月22日、遍路の続きを始めました。その前に、前回撮り忘れていた円明寺の本堂を撮影し、カラーのお姿をもらい忘れた玉蔵院により、五十四番札所延命寺のある今治市へと向かいました。
遍路道は旧北条市内の県道を進むようになっており、途中で鎌大師という霊場もあるようです。バイクのためそれっぽいお堂は見えたのですが、後続車のこともあり素通りしてしまいました。時間を短縮を重視するのであれば北条バイパスを利用した方が早いです。
左手に瀬戸内海を見ながら国道196号を今治市方面へと向かっていきます。国道から今治市内へと入るY字路に看板が立っているので、そこを左に入り看板に従い進んでいくと、延命寺さんに到着します。
五十三番は圓明寺、五十四番は延命寺、どちらも「えんめいじ」とも「えんみょうじ」とも読めるなと思っていたら、昔は両方「えんみょうじ」だったそうです。四国遍路が確立し、ややこしいため、五十四番は地元の方が愛称として使っていた「えんめいじ」を正式名にしたそうです。
仁王門の右に細い車道があり、駐車場へはこの道を使っていきます。境内をちょっとかすめるような形で車道が続いているため、地元の方とおぼしき車も何台か通り抜けていました。駐車場の仁王門側に鐘楼があり、地元の篤志家の働きによって、大戦中も鉄不足で没収されるのを免れたという説明がありました。鐘をつく棒はありましたが、勝手につけないように縛られてありました。特別な時にのみつくようです。
駐車場から本堂に向かって進むと、山門があり、今治城で使われていたものを移転した門であるという説明書きがありました。山門をくぐると、右手に別の鐘楼があり、こちらの鐘は参拝者が自由についていいようになっていました。
山門の左には薬師堂(だったはず)、土産物屋、納経所と一列に並んでいます。土産物屋あたりの建物は、近所で廃校になった小学校の校舎を移築しているという説明がありました。山門といい他の建物といい、古くからあるものを引き継いでいるという点が印象に残りました。境内は比較的フラットです。
正面の石段を数段登ると本堂があり、そこから左にある石段をさらに登ると大師堂があります。つくことのできる鐘楼の横あたりから歩き遍路用の道が延びており、その近くには四国で二番目に古い道標や、大飢饉の際にも餓死者を出さなかったこの地の庄屋の墓石なんかもありました。歩き遍路用に目印やおよその距離を書いている看板が立てられていたので、迷わず進めそうです。
8時前で参拝者もまだ少なく、すがすがしい気分で遍路がスタートできました。