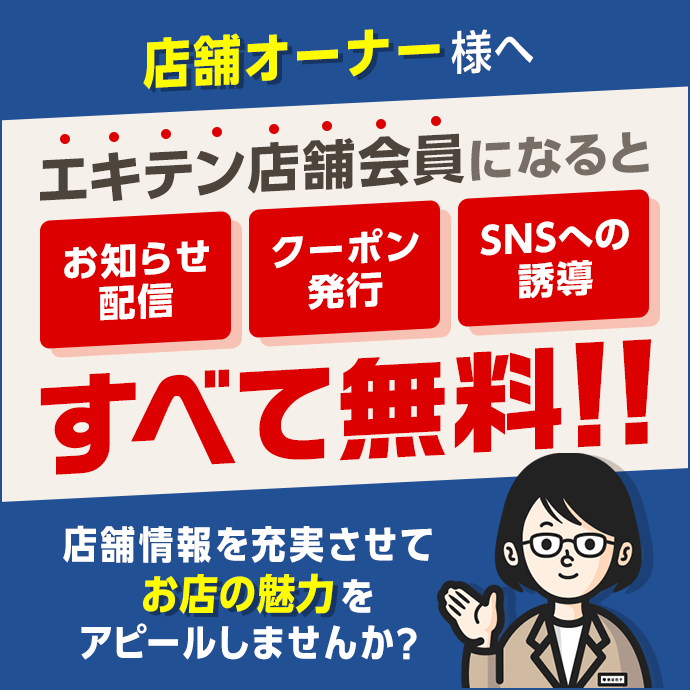口コミ
四国八十八ヵ所巡礼の旅で参拝しました。松山市街から車で20分足らずのところにある真言宗智山派の寺院で、四国八十八ヵ所霊場の第五十二番札所です。参道入り口から50段ほどの石段を上って行くと重要文化財に指定されている風格ある仁王門があり、その先に間口7間、入母屋造り本瓦葺きの大きなな国宝の本堂があります。その他にも歴史を感じる立派な太子堂や鐘楼、眼病平癒にご利益ある一畑薬師、一回まわせばお経を一巻読んだのと同じ功徳が得られる摩尼車など多くの伽藍や像がある興味深いお寺でした。
四国八十八ヵ所霊場の第五十二番札所です。瀧雲山・護持院と号す真言宗智山派の寺院で、創建は用明天皇2年(587年)、開基は真野長者と伝わる古い歴史を持っています。鎌倉時代の作で国の重要文化財に指定されている二の門の仁王門を潜り、しばらく坂道を進み石段を上ると四天王をまつる二層の楼門があり、その先正面に国宝に指定されている伊予最大と言う本堂があります。駐車場から国宝の本堂までは坂道がだらだらと続き、途中45段の石段もあり少し時間がかかりますが雰囲気はよかったです。
四国八十八ヶ所巡りの52番札所です。
山門を通り過ぎ、しばらく歩くと、まず納経所が見えてきます。
ここに整備された駐車場が有ります。
そこから更に上ります。
すると、お大師様や大日様、観音さま、地蔵菩薩様が出迎えて下さる手洗い場に辿り着きます。
手を洗って階段を、登りますが、中々の階段です(//∇//
参拝するまでに沢山の自然を目にする事が出来る壮大なお寺でした!
9月15日、台風接近中の雨の中、遍路の続きへ出かけました。仕事の都合で夕方には愛南へ戻らなければならないため、前回廻りきれなかった松山市内の3札所を打つことにしました。
石手寺からだと、平和通りか樋又通りを経由して中央通り(国道437号)を三津浜港方面へ進みます。途中JR三津浜駅前(県道19号)へ右折して松山観光港方面へ進むと看板があるのでそこを右折し、看板に従って進むと迷うことはありませんでした。
参道の入口に一の門があり、まっすぐ進むと、二の門として仁王門があります。駐車場は仁王門の右の道を150m上がった所と、そこからさらに300m上がった本堂近くにもありました。上の駐車場を知らなかったのと、仁王門をくぐるために下の駐車場にバイクを止め、仁王門をくぐり歩いて行きました。途中には眼病に御利益のある一畑薬師のお堂などがあります。
二の門から本堂までの間に納経所があります。大きな建物があり、宿坊だと思っていたのですが、後で調べたら庫裡だそうです。
最後の石段を登り、三の門(四天王門)をくぐると、正面に国宝の本堂があります。現大分県臼杵市の長者が難波に向かう途中、高浜沖で暴風雨に遭い、念仏を唱えると、山から光が差し込み、無事に避難できました。光の差した山に行ってみると、十一面観音を祀ったお堂があったそうです。感銘を受けた長者は臼杵に帰ると大工に木組みを造らせ船に乗せ、再びこの地にやってきました。そして、一夜で木材を組み立て、本堂を完成させたため、「一夜建立の御堂」と呼ばれるようになったという伝説が残っています。また、本堂には最古の木製納札が納められており、西暦でいう1780年の年号が書かれているそうです。
境内の右には鐘楼堂があり、その奥には聖徳太子堂もあり、合格祈願に御利益があるそうです。聖徳太子堂の近くには昔力比べに使われた「亀の石」もあります。
本堂左の石段を登ると大師堂があります。大師堂の左には、三重の塔が建っていたときの礎石が残っており、この石のくぼみを新品のたわしでこすると、痔が治ると言われています。ガイドブックで事前に読んでいたので、前日にスーパーで亀の子たわしを購入し、持参しました(たまに初期症状が見られるので)。しかし、特に説明の看板もなく、三重の塔が建っていたにしては平地が狭い場所なので、探すのに手こずりました。説明を書いたら恥ずかしがって磨く人がいなくなったからでしょうか?先客の人が使ったたわしを置いていっているので、私も磨いた後に置いてきました。御利益は薄いかもしれませんが、たわしを持参しなくても置かれているたわしでお参りはできます。ですが、効果は新品の方がありそうなので、深刻に悩んでいる方は新品を持参し、念入りに磨きましょう(笑)