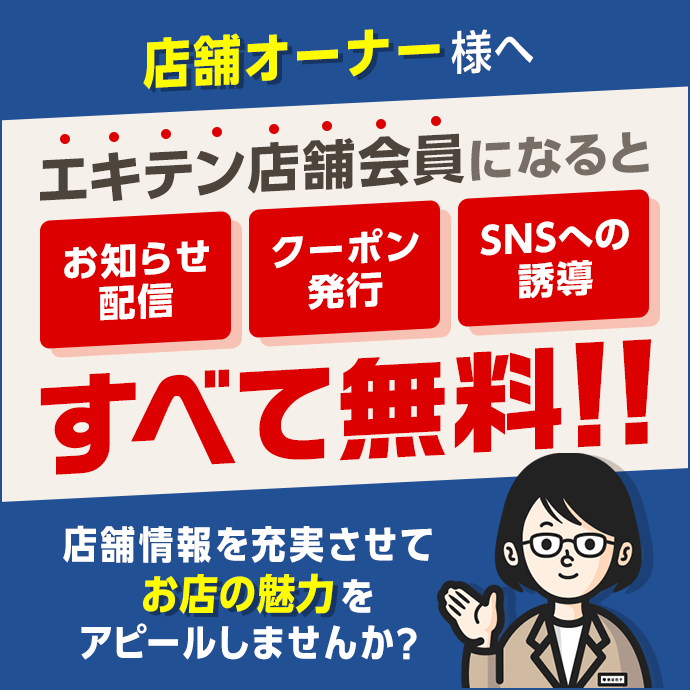口コミ
四国八十八箇所巡礼の旅で参拝しました。高松自動車道 善通寺ICから車で10分ほどのところにある四国八十八箇所霊場の第七十三番札所です。奥の院には7歳の弘法大師が「仏門に入って多くの人を救いたい」と身を投げたところ、釈迦如来と天女が現れて救済したという言い伝えがある「捨身ヶ嶽禅定」があります。奥の院まで歩くのは大変そうだったので、境内にある「捨身ヶ嶽遙拝所」からご宝号を唱え、祈願させて頂きました。
四国八十八箇所霊場の第七十三番札所です。鐘楼門を入ると、正面に本堂、その右手に大師堂、左手に虚空蔵堂が建っています。境内から50分ほど登った所に7歳の弘法大師が仏門に入って多くの人を救いたいと身を投げたところ、釈迦如来と天女が現れて救済したという言い伝えがある「出釈迦寺奥の院 捨身ヶ嶽禅定」がありますが、そこまで行けそうもないので境内にある「捨身ヶ嶽遙拝所」で参拝しました。小さい境内ですが、美しくコンパクトにまとまっていて高台からは讃岐平野や瀬戸内海がよく見えました。
四国八十八箇所霊場の第七十三番札所
- 投稿日
曼荼羅寺から約500m山に向かって進んだところに七十三番出釈迦寺(しゅっしゃかじ)があります。徒歩でも十分に行けます。駐車場は曼荼羅寺よりは広いので、曼荼羅寺が混んでいたら出釈迦寺の駐車場に車を置いて、徒歩で下りて曼荼羅寺を参拝し、また歩いて出釈迦寺へというのも一つの手かもしれません。山号がどちらも同じで距離も近いことから、元は1つの寺だったのではという説もあります。
国道沿いからもえらい山奥に立派な建物が見えるので、あれが札所か!?と思いましたが、山のてっぺん付近に見えるのは捨身ヶ嶽と呼ばれる出釈迦寺の奥の院でした。太龍寺の舎心ヶ嶽とは由来が異なります。
出釈迦寺自体はそこまで広い境内ではなく、山門を入って右側に本堂と大師堂が並んでいます。本堂左に石段があり、そこを上がると地蔵堂があります。また、奥の院遥拝所もあり、ここで念仏を唱えると捨身ヶ嶽に参拝したのと同じ御利益が受けられると言われています。
しかし、今までも近くに何かあれば立ち寄っていた私のこと。目の前に捨身ヶ嶽が見えるのに寄らずに帰るわけにはいきません。所要時間は徒歩約50分が相場と言われています。納経所左の裏口から出て、電線に沿ってみかん畑の広がる農道を上っていきます。すると登山道のような参道の入口につきます。ここまでは車で上ってくることもできます。頂上まで車で行くこともできますが、有料です。途中でチェーンが掛かっているので、車で上がる場合は納経所で確認をしたほうがいいでしょう。
登り始めて間もなく万病に効くといわれている霊水が手水場としてあります。参道は勾配が急で、徒歩ではかなり大変です。弥谷寺の奥の院は苦労せず参拝出来た分、ギャップで余計に大変に感じました。途中には曼荼羅寺の西行法師昼寝石とセットのような形で、西行法師の腰掛石もあります。
それでも山頂付近にある禅定場所までは約30分で到着できました。50分も掛からないじゃないかと思いましたが、正式な霊場までは、奥の院本堂横を通ってさらに岩山を登っていきます。本堂横の通路には「警察予備隊時代の落書き」が残っており、昔は行軍の練習にこの辺まで登山に来ていたようです(現代人の落書きは絶対いけません!)。この付近は登山コースにもなっているようですが、中級者以上向けのようです。鎖を伝って登っていくと、「捨身誓願之聖地」と書かれた札の立つ場所があります。ここが正式な捨身ヶ嶽の地のようです。立て札のさらに先まで行ってみましたが、我拝師山の山頂に出て、さらに隣の山へと道が続いています。切りが無いのでここで引き返しました。
弘法大師が7歳の頃、ここまで登り「私はこれから仏門に入り、多くの人を救いたいと思う。この願いが叶うなら釈迦如来よ姿を現し給え。叶わぬならここから飛び降り、この身諸仏に捧げる」と祈ってここから崖下に飛び降りたそうです。すると、釈迦如来と天女が現れ、弘法大師の体を抱きとめたといわれています。
絶壁ではないので落ちたら岩肌に体をぶつけながら転がっていきそうですが、確かにここから落ちたら命はないなという場所です。弘法大師の仏門に対する意気込みが感じられるエピソードです。
ここまで来る人はそういないようですが、4組の参拝者やハイキングの方に会いました。
納経所に戻り、本坊と奥の院の2つの納経をしてもらいました。捨身ヶ嶽に登らなくても、境内の遥拝所をお参りしただけでも奥の院の納経はしてくれます。
予想以上に時間が掛かりましたが、札所の密集地帯なのであと2つは廻れるかなと思い後にしました。