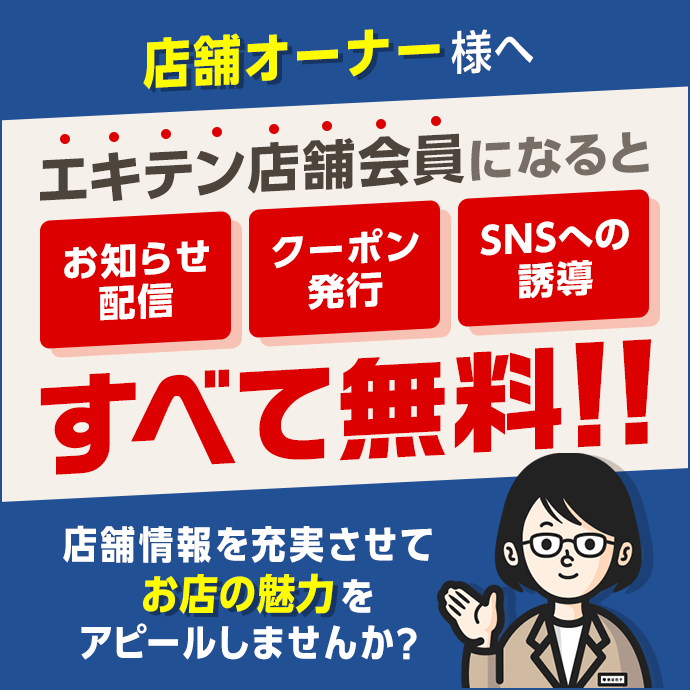口コミ
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。四国八十八ヶ所霊場の第7番札所です。大同年間に弘法大師がこの地を巡教して逗留されたときに阿弥陀如来を感得し、如来像を刻んだのが本尊として祀られたと伝わる古い歴史を持つ寺院です。大師は人々が「八つの苦難」から逃れ、光明に輝く「十の楽しみ」が得られるよう山号を光明山、寺号を十楽寺とされたと伝えられています。下が白、上が朱色の中国風の鐘楼門を潜ると多くの水子地蔵が祀られていて、階段を上ると本堂があり、本堂左手に眼病や失明に霊験があるとされる治眼疾目救歳地蔵尊が祀られています。眼病に悩まれているのかたくさんのお遍路さんが参拝されていました。
四国八十八ヶ所霊場の第7番札所です。光明山と号す高野山真言宗の寺院で、創建は大同年間(806年 - 810年)、開基は弘法大師と伝わる古い歴史を持つ寺院です。竜宮門形式の山門を入ると前に水子地蔵が祀られていて、大師堂の横に古くから眼病を治すご利益があるとされる治眼疾目救済地蔵尊が祀られていて、歴史を感じる雰囲気のいい寺院でした。
安楽寺を出てそのまま西へ約1km進むと十楽寺です。県道139号線沿いから進行方向に向かって少し右に入ります。私は看板を見落として国道318号線との交差点まで進んでしまいました。徳島自動車道の高架をくぐってしまうと行き過ぎですので参考までに。
鐘楼門をくぐるとすぐに水子地蔵が並んでおり、鐘楼門の赤と同じくらい前掛けの赤が目に入ってきます。
山門をくぐると正面に本堂、左奥の石段を登ったところに大師堂があります。納経所は右手にあり、近代的な建物で宿坊も兼ねているようです。
山門の中に入ることができ、階段を上った先に愛染明王の像があります。人間関係だけでなく、仕事など良縁を結んでくれるというご利益があると説明書きがありました。
また、失明した人や目の病気を治してくれるという治眼疾目救歳地蔵尊が有名で、本堂の左にある朱色の祠?の中にまつられています。
十楽寺を出発したのが4時前。通り過ぎたロスが響き、きりがいいので十番まで回っておきたい、けれど回るだけで参拝をおろそかにするのも失礼な気がする…。という微妙な時間となりました。密集はしているもののここからは4〜5kmずつ離れているので迷いどころでした。