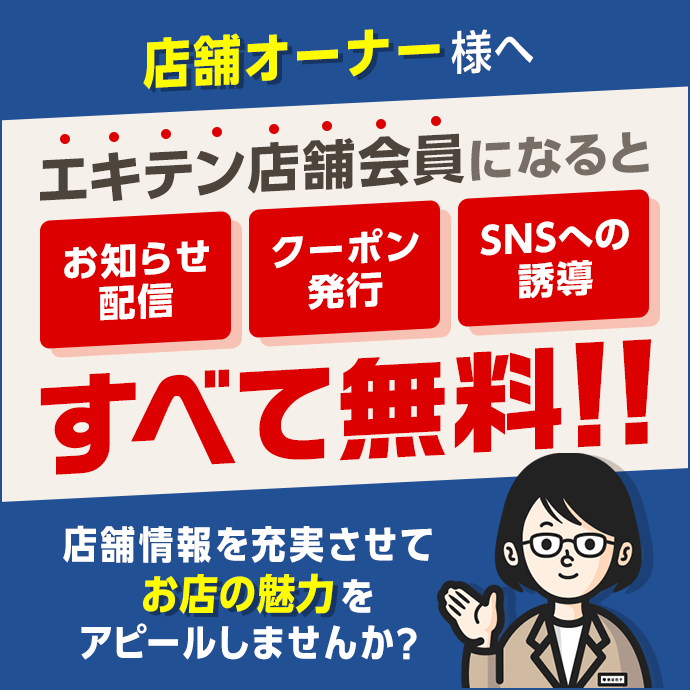口コミ
四国八十八ヶ所巡礼の旅で参拝しました。四国八十八ヶ所霊場の第十七番札所です。阿波10代藩主・蜂須賀重喜公が大谷別邸から移築したという仁王門は四国最大と言われる仁王様が祀られていて、大きなワラジも飾られていてすごく迫力がありました。境内にある弘法大師が掘ったとされる「面影の井戸」は自分の姿が映れば無病息災、映らなければ三年以内に不幸が訪れるといわれています。私は怖くて覗けませんでしたが、勇気のある方は覗いてみてください。
四国八十八ヶ所霊場の第十七番札所です。阿波10代藩主邸から移築された立派な山門を潜ると広い敷地の中に本堂や太子堂などの建物が点在しています。境内には弘法大師が掘ったと伝わる「面影の井戸」があって、「覗き込んで自分の姿がうつれば無病息災、うつらなかったら3年以内の厄災に注意する」と書いてあって、怖くてのぞき込むことができませんでした。
四国88ヶ所の17番札所になります。名前の由来となっている、おもかげの井戸があります。弘法大師がこの辺りが濁水なのをあわれみ、錫杖で一夜のうちに、井戸を掘られたところ、清水が湧き出して、井戸寺と命名されたそうです。
興味深い言い伝えです。
観音寺を出て右に進み、神社とお寺の間を左折し、県道29号へと入ります。国道192号をまたぎ、府中駅東の踏切を渡ってまっすぐ進むと本日の最終目標に定めた17番井戸寺があります。
駐車場は本堂の真裏に位置しているので、外周を半周歩いて仁王門(正面)に入ります。
今回参拝した10〜17番までの中では唯一の朱塗りの山門で、大きさもこれまでの中で一番大きかったです。
境内には、名前の由来となった、弘法大師が一夜にして掘ったという伝説の井戸も残っており、のぞき込んで自分の顔がうつれば無病息災、映らなければ三年以内に不幸が訪れるという、金泉寺の井戸に似た言い伝えがあります。なお、容器代100円を払うと、井戸の水を持ち帰ることが出来ます。
薬師如来7体が御本尊という珍しいお寺でもあります。正面に本堂、右手に大師堂があります。
また、納経所の近くに日限(ひぎり)大師もまつられていますが、「日限大師へ願い事をするときは、3日や5日といった日を決めて連続してお参りしないと御利益がないので、お参りする人は少なくとも明日・明後日も参拝出来る人だけにしてくださいね(笑)」と、居合わせたお遍路ツアーのガイドさんが説明していました。
以上で2回目の遍路の目標は達成したのですが、地図を見ると別格2番も帰りながら立ち寄れそうだったので、参拝することにしました。