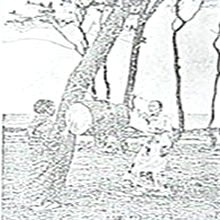教室料金
¥2,500(非課税)
和太鼓体験レッスン : お一人 1500円
※バチはこちらでお貸しいたします。
体験レッスンを経て自分にも続けられそうだと判断していただきましたら、次回来られたときから正式入会となります。
【正式入会】
大人 : 1回 2500円 (高校生より)
子供 : 1回 1500円 (中学生料金)
※入会金は不要です。
※お月謝制ではありませんので教室に来られたときだけ料金をお支払いください。
※教室の時間は13:00~16:45の3時間45分です。最後までおられてお稽古されても途中で帰られても自由です。
- 注意事項
教室には動きやすい服装とシューズでお越しください。
※サンダルやヒール、スカートでのお越しはご遠慮ください。- 利用条件
入会は中学生からとさせていただきます。上の年齢制限はありません。