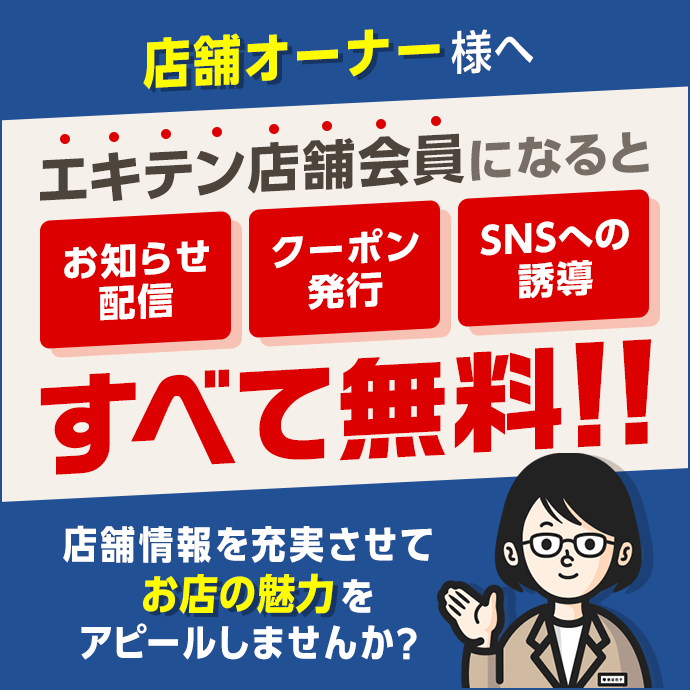還源山妙覚院浄光寺 天台宗で開残1200年の歴史を有する超古刹です
口コミ
日光市匠町の閑静な住宅街にあるお寺です。
街道から奥に入った細道にあるので、あまり知られない場所となります。
1200年以上の歴史ある天台宗のお寺ですが、境内のお地蔵様や石碑などが印象的なお寺で見応えがあります。
前回訪れた時に見損じた文化財を見に訪れました。広い境内なので何処にあるか分からず庫裡にあるブザーを押してお寺の人を呼び場所を教えて頂きました。それは境内の墓地の一番高い場所にありました。座禅院権別当の墓(日光市文化財)です。1445年~1607年頃の権別当6基の墓碑です。日光山の山務を執った人達の墓で等間隔で1列に並んでおりました。全て五輪塔で何れも欠けることなく状態が良好で青みがかった色合いがイイです。別当の墓の上り口に石造 阿弥陀如来坐像・地蔵菩薩坐像(日光市文化財)がお堂の中に祀られております。小さなお地蔵様2基が前方で後方の文化財のお地蔵様を護衛しておりました。後方左右のお地蔵様(阿弥陀如来坐像、地蔵菩薩坐像)は1596年、1636年の造立で総高148cm、140cmありドチラもお顔の風化が表情を見えにくくしていましたが気にせず一心不乱に座禅を組んでおられました。中央の総高184cmと一際高い1550年造立の地蔵菩薩坐像はふくよかな出で立ちで凛々しいお顔立ちをしておりました。コノお堂のリーダーらしい御姿だと感じました。別当の墓もお地蔵様も味のある文化財です。
山門前に日光型庚申塔・庚申灯籠(日光市文化財)が並んでおります。10基以上並んでおりますが指定された物は5基でココには4基の先が三角の庚申塔が当てはまり日光山らしい独自の形状だと思いました。灯籠はココには無く本堂前で見られます。山門を入ってスグに梵鐘(栃木県文化財)があり日光山最古である1459年の造立で戦時の供出もモチロン免除された鐘です。江戸時代の鐘は数多く見ておりますが室町時代の鐘は初めて見ました。江戸時代の物と違って彫刻などは見られませんが縦横に刻まれたラインが特徴的でありました。残念ながら亀裂が入っているそうで音色は聞くことは出来ないそうです。推定樹齢550年のヒノキが珍しい形状です。その理由は長年盆栽仕立てで育てたからだそうで幹もそうですが枝も太く圧力が半端ない木です。憾満ヶ淵に並ぶ地蔵の御首があります。1902年の大谷川の大洪水で流され川床に沈んでいたのを地元の人がお寺に安置したそうです。これだけ大きな御首の物が胴体と切り離されて流れるとは想像を絶する事態だったに相違ありません。耳を澄ませば当時の阿鼻叫喚が聞こえてきそうです。御堂内に菅笠日限地蔵尊が祀られていて全国で珍しい菅笠をかぶったお地蔵様だそうです。全身を赤づくめのコーデで包んでいるのは見慣れておりますが菅笠をかぶると托鉢をしているお坊さんに見え思わず小銭を投げ入れました。随分と印象が変わるなあと思いました。墓地の手前に防火隊碑(日光市文化財)があり1843年に建立したもので八王子の同心との長い協力体制を物語る記念碑です。命令とはいえ210余年の間に世代を超え日光で消火活動をした八王子の同心には頭が下がる思いです。冒頭に述べた1637年建立の庚申灯籠が本堂前にあり火袋には活発な二猿が陽刻されておりました。この地域ならではの物を数多く拝見することが出来ました(写真を参照して下さい)。
口コミ投稿で最大25ポイント獲得できます
写真
あなたの写真投稿がこれからお店を訪れる人の参考になります。
概要
店舗名
ジャンル
電話番号
住所
アクセス
関連ページ
- 公開日
- 最終更新日