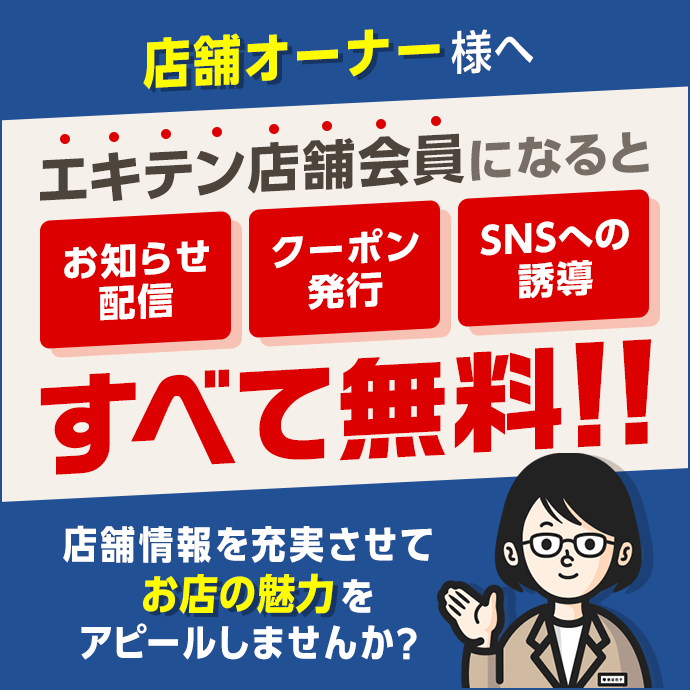口コミ
県道194号をさらに松山市方面へと進んでいきます。かなり細い道ですが、路線バスも通ります。しかし、そこは遍路道、近隣のドライバーも勝手が分かっており、譲り合い精神で往来しています。八坂寺から1kmくらい進んだところに、別格九番の文殊院があります。
浄瑠璃寺・八坂寺・文殊院と、この近辺には衛門三郎の伝説が残っています。弘法大師がこの地を訪れ、托鉢をしていたとき、欲深いこの地の庄屋、河野衛門三郎は托鉢を7日間断り、8日目に竹箒で鉢をたたき落とすと、鉢は8つに砕け、周囲の山に飛び散ったそうです(そこから加持水が湧いたという話も)。すると翌日から衛門三郎の8人の子供が毎日1人ずつ奇病で亡くなっていき、托鉢をしていた僧が弘法大師だと知ります。夢で大師から「私に会えたら罪を許そう」というメッセージを聞き、衛門三郎は四国遍路へと旅立ちます。20周したけれど大師には会うことができず、逆に回れば会えると考え(逆打ちの発祥とされる)、反時計回りに遍路を続けましたが、12番焼山寺で力尽き倒れました。すると弘法大師の声がし、無事に巡り会え罪を許してもらえたと言われています。
この文殊院は、弘法大師が衛門三郎の亡くなった8人の子供の供養と悪因縁切りの修法をした四国唯一の霊場だそうです。
衛門三郎のこの行為が四国遍路発祥とされ、この逸話の中には納札の原型になったであろうエピソードなんかも含まれています。
子供への戒めも兼ねて、「悪さをすると罰が当たる」という要素を盛り込んだのだと思うのですが、昔話を鵜呑みにすると、弘法大師は自分に刃向かうものを呪う恐い人というエピソードだらけになってしまうな、と少し思ってしまいました。
山門はなく、境内はこぢんまりとしており、本堂・毘沙門堂・大師堂があります。納経所の机の横には猫がひなたぼっこをしており、のんびりとした感じでした。
文殊院周辺には八塚や加持水の湧いた場所など衛門三郎伝説にまつわる場所が点在しているようなので、それらも訪問してみると四国遍路の由来がよく分かるかもしれません。
口コミ投稿で最大40ポイント獲得できます
写真
あなたの写真投稿がこれからお店を訪れる人の参考になります。
概要
店舗名
ジャンル
電話番号
住所
アクセス
関連ページ
- 公開日
- 最終更新日